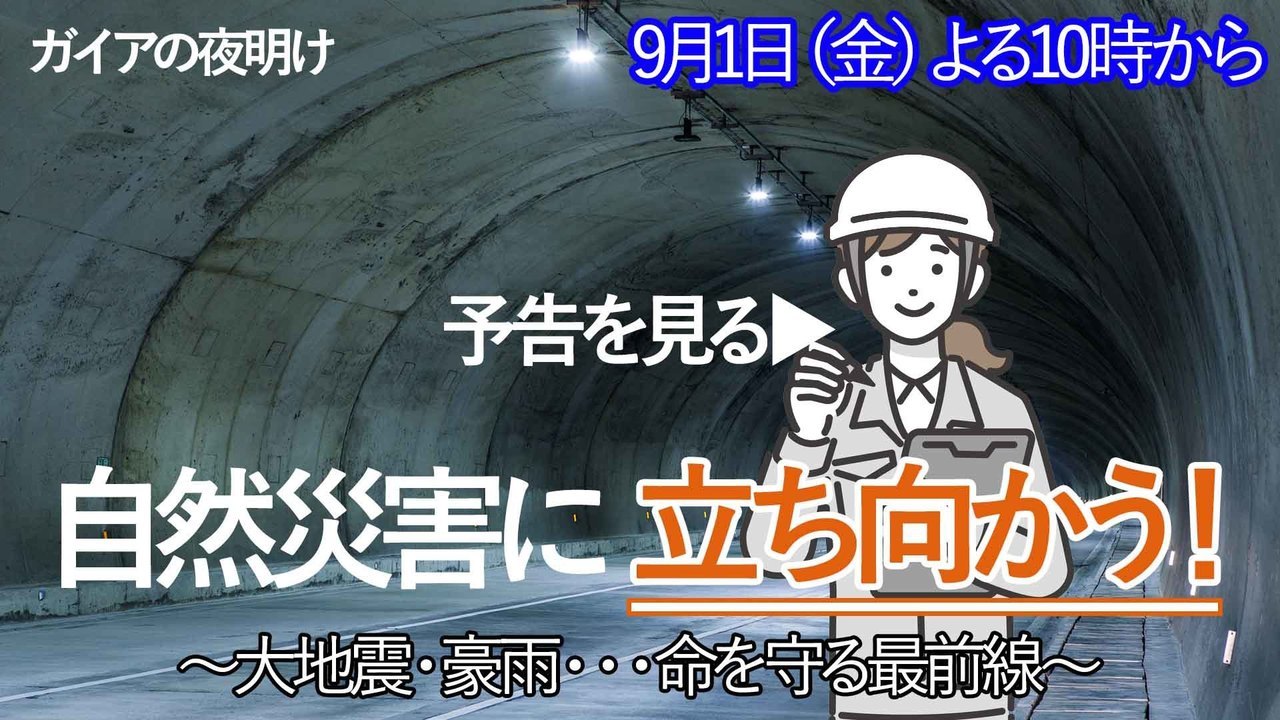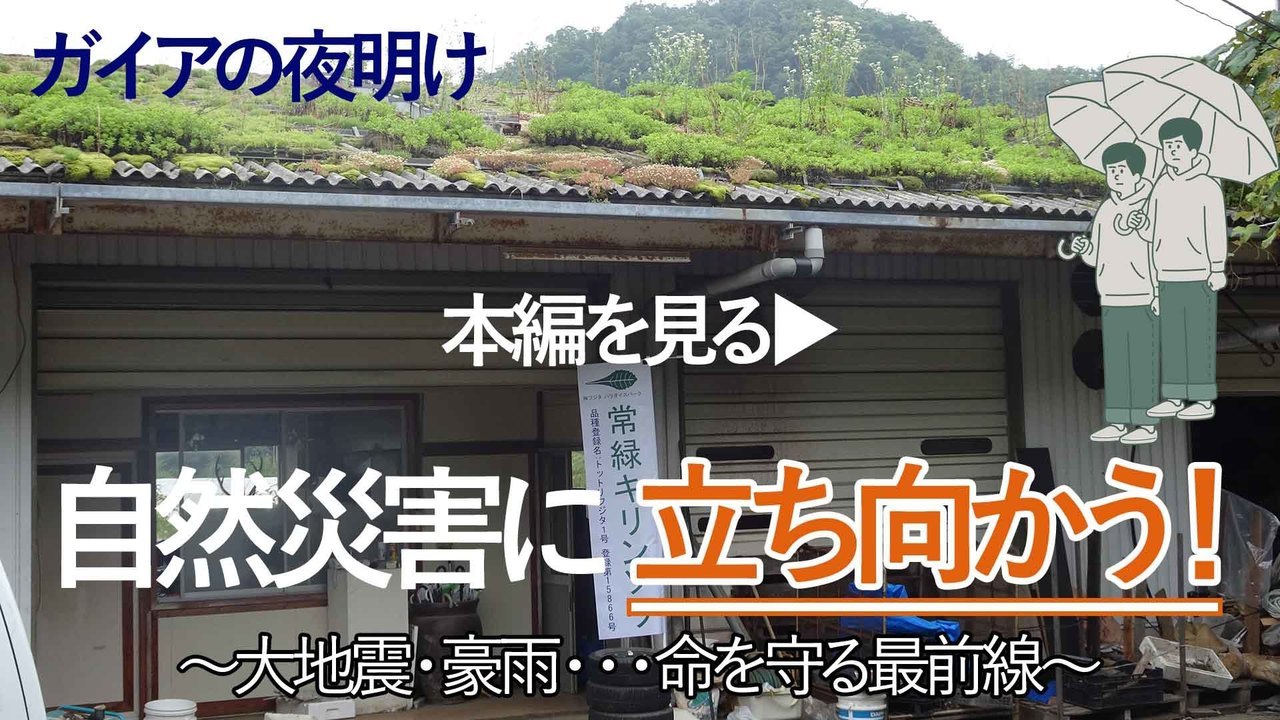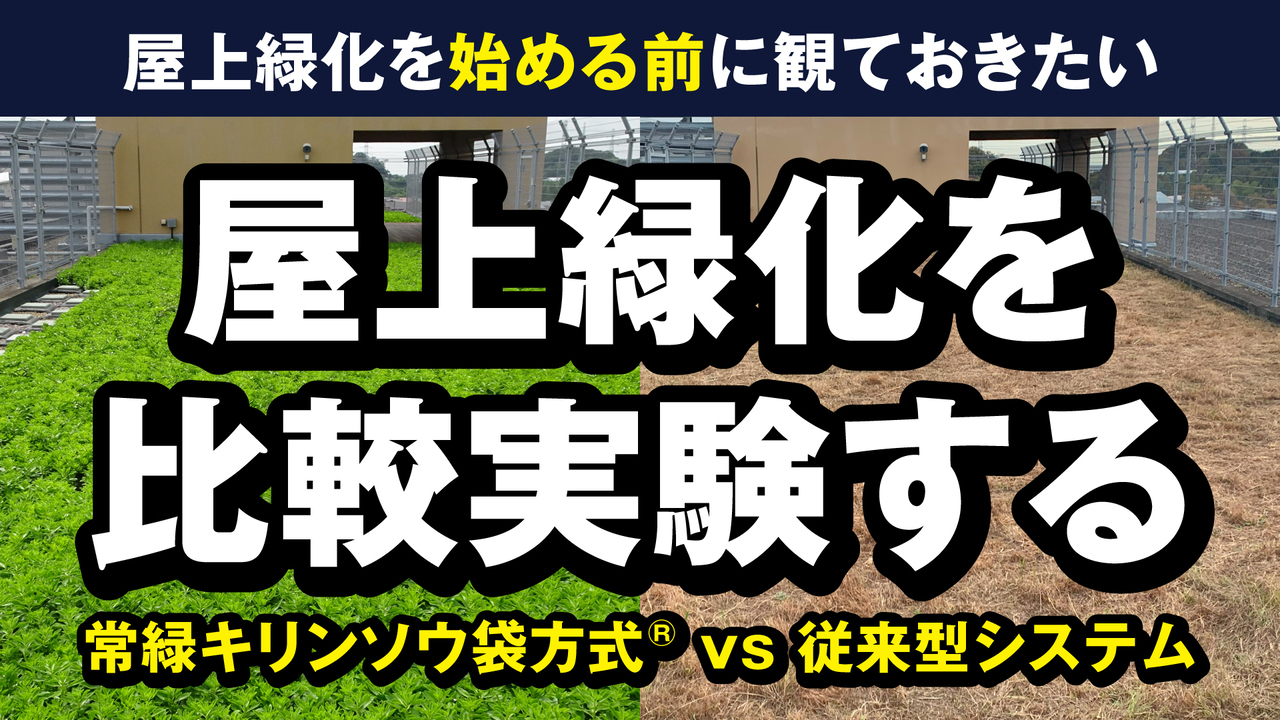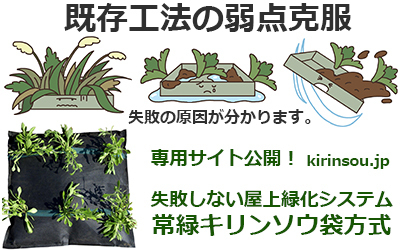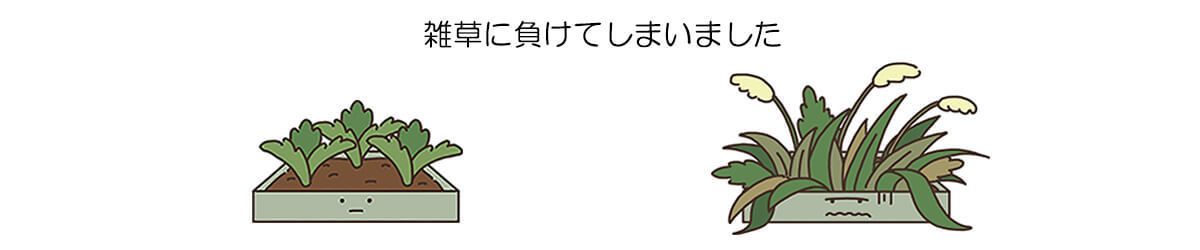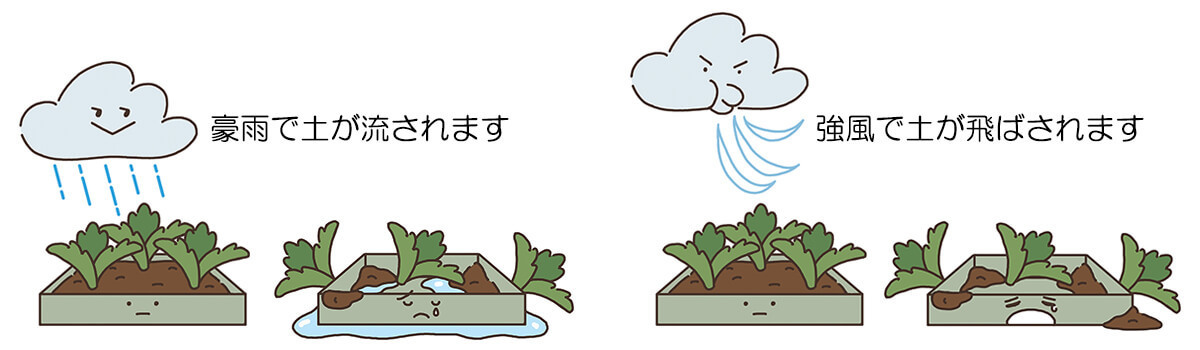品種保護対策に関して よく寄せられる質問1
よく寄せられる質問(農研機構・種苗管理センターHPからの抜粋)
侵害状況記録の作成について
問1
登録品種が無断で増殖され、販売されている情報をつかみました。店頭で販売している侵害品について侵害行為の証拠を作りたいのですが、どのように対応すればよいのでしょうか。
答え
店頭で販売されている侵害品を入手し侵害行為の証拠にするためには、入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に証明する必要があります。さらに、入手した侵害疑義物品は利害関係者ではない第三者に預けるのが一番確実な方法です。
種苗管理センターでは品種保護Gメンを平成21年度からは全国7ヶ所(北海道、青森県、茨城県、長野県、岡山県、長崎県、沖縄県)に配置し、このような場合に依頼者とともに侵害行為の現場に行き、入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に記録する侵害状況記録書を作成するサービスを行っています。また、入手した侵害疑義物品を預かる寄託も実施しています。さらに、入手した侵害疑義物品が切花の場合には挿木による種苗の生産も行っています。これらは有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
問2
違法な栽培をしている農家についての情報が寄せられました。権利者が直接その農家へ確認に行くと拒絶されるおそれがあるので、品種保護Gメンに調査してもらえますか。
答え
品種保護Gメンには物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼により品種保護Gメンが単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。
したがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手したり、相手側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。その際、品種保護Gメンは、権利者が侵害疑義物品を入手したり侵害状況を確認する現場に立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成することになります。
品種類似性試験について
問3
品種類似性試験(DNA分析を除く。)を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
答え
品種類似性試験依頼書及び試験に供する登録品種と比較品種の種苗等を提出してください。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。1.試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。2.試験の依頼者は育成者権者、専用利用権者若しくはその代理人又は育成者権侵害を訴えられた者若しくはその恐れがある者でなければなりません。試験は有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
問4
品種類似性試験の特性比較と比較栽培とは何が違うのですか。
答え
特性比較は、依頼者が提出した品種と登録品種の植物体の特性を目視及び計測により比較調査しますので、簡易・迅速に類似性の程度について客観的資料を得ることができます。ただし、栽培条件の違いにより、特性の発現が異なる場合が多く、期待した結論が得られないことがあります。
比較栽培は、依頼者が提出した種苗を栽培試験と同一の方法で栽培し特性を比較調査しますので、信頼性の高い結論が得られます。ただし、侵害品からの植物体の再生が困難な場合があるほか、栽培適期が限られ、試験に長期間を要します。
両者はそれぞれ長所と短所がありますので、特性比較と比較栽培を組み合わせることでそれぞれの結果を有効に活用することができます。
問5
DNA分析による品種類似性試験を依頼したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
答え
種苗管理センターでDNA分析が実施可能な植物(品種)は、いちご、おうとう、白いんげんまめ、茶、日本なし、小豆、ひまわり、とうもろこし、カーネーション、りんご、パインアップル及びばれいしょの登録品種、いぐさの「ひのみどり」に限定されます。また、稲、白いんげんまめ、小豆、いぐさ等については他の検査機関等が実施しています。
当センターのDNA分析を希望される場合は、品種類似性試験依頼書及び試料(通常、いちご及びおうとうの果実は30個、白いんげん豆の子実は30粒、いぐさの茎は30本、苗は10株)を提出してください。提出された試料から無作為に抽出したサンプルを分析します。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。1.試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。2.試験の依頼者は育成者権者、専用利用権者又はその代理人若しくは育成者権侵害を訴えられた者又はその恐れがある者でなければなりません。試験は有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
品種の利用について
問6
種苗法第2条第5項に「譲渡の申出」がありますが、育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトで登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をした場合について質問します。
1.育成者権者の許諾を得ない他人が、インターネットのサイトに登録品種の名称を表示し、種苗の譲渡の申出をする行為は、それだけで育成者権の侵害になるのでしょうか。
答え
育成者権の侵害に該当することになると考えられます。
ア. 「譲渡の申出」(種苗法第2条第5項)が利用行為に含まれているのは、「譲渡の申出」は、それ自体では育成者権者に実質的な不利益を与えるものではありませんが、実質的不利益を与える「譲渡」の前提行為であり、「申出」がされれば「譲渡」がされるおそれが高いことを踏まえて、定型的に「申出」にも育成者権の効力を及ぼすことが相当と考えられたためと考えられます。そうしますと、登録品種の名称を表示して、種苗の譲渡の申出をする行為は、当該登録品種の種苗についての「譲渡の申出」に該当することになると考えられます。 よって、育成者権者の許諾を得ない他人が、「譲渡の申出」を行った場合は、育成者権の侵害に該当することになると考えられます。
イ.登録品種の名称Aを表示し、実際には登録品種Aではなく種苗Bを無断販売する行為について
申出において譲渡の対象として表示された品種名称と、実際に譲渡の対象として考えている品種とが異なる場合には、表示された品種が譲渡されるおそれはなく、その育成者権者は実質的な不利益を被らないことになります。 このような場合にまで、育成者権の効力を及ぼす必要性は低いように思われます。したがって、そのような場合は、そもそも表示された品種の譲渡の申出に該当しない、 又は譲渡の申出には該当するが育成者権の効力を及ぼすことは信義則に反する(刑事事件においては、刑事責任を問うほどの違法性がない)と解される可能性があります。
よって、例えば、インターネットのサイト上に、登録品種「A」の種苗を譲渡する旨の記載がされていたとしても、その申出人が実際に譲渡しようと考えている種苗が「A」ではなく「B」であったような場合には、「A」の譲渡の申出に該当しない、又は「A」の譲渡の申出には該当するが「A」の育成者権の効力を及ぼすのは信義則に反する(違法性がない)として、「A」の育成者権の効力が及ばないとされる可能性があると考えられます。
ウ.譲渡の申出をしたが、譲渡される可能性がなかった場合
譲渡の申出をしたが、譲渡される可能性がなかったような場合も、イと同様に解される可能性があります。
もっとも、登録品種「A」の種苗を譲渡するつもりで、登録品種「A」の名称を使用して、譲渡の申出を行ったけれども、譲渡の申出の時点では申出人の手元に「A」の種苗がないような場合については、当該時点で手元にないということだけでは、 必ずしも譲渡の可能性がないとはいえないのではないかと思われます。その時点で手元になくとも、その後に第三者から「A」の種苗を取得などして、譲渡できる可能性があり得ますので、そのような場合であれば、育成者権の効力が及ぶと解すべきと考えられます。
このように解しますと、イ及びウのような場合には「A」の育成者権の効力が及ばないことになりますが、種苗法第22条2項、不正競争防止法又は刑法等により対応することが可能と思われます。
2.1が侵害であるとした場合、育成者権者側の侵害の立証は、譲渡の申出をしたという広告の証拠だけで十分でしょうか。 それとも、譲渡の申出をした者が持っている種苗が登録品種であることを立証する必要があるのでしょうか。
答え
1のイの記載のとおり、譲渡の申出の対象である種苗がその育成者権者が権利を有する登録品種でなかった場合、育成者権の効力が及ばない可能性があります。
この点、1のイの例で「A」について譲渡の申出がないと解するのであれば、育成者権者が譲渡対象が「A」であることについてまで立証する責任を負うと考えられます。他方、「A」についての譲渡の申出はあるが信義則違反であると解するのであれば、被告が譲渡の対象が「A」ではないことを立証する責任を負います。
そして、前者のように解するとしても、その登録品種の名称「A」を使用して譲渡の申出をしているとの事実は、その譲渡の申出の対象となっている種苗が登録品種「A」であることをうかがわせる有力な事実になると思われます。また、民事訴訟になった場合、譲渡の申出人は、その申出の対象が登録品種であることを否認する場合には、そのことについて具体的に明らかにしなければならないことになります(種苗法第36条)。よって、育成者権者がその登録品種の名称を使用して譲渡の申出をした事実を立証したにもかかわらず、申出人が相当な理由なくそれが当該登録品種ではないことについて具体的に明らかにしない場合には、その譲渡の申出の対象は当該登録品種であると裁判所に認定される可能性があると考えられます。
3.育成者権者の承諾を得ない他人が、登録品種の種苗を用意しないまま、登録品種の名称を表示し、 種苗の譲渡の申出をする行為は育成者権の侵害になるのでしょうか。
答え
1のウの記載のとおり、譲渡の申出の時点で種苗を用意していなかったとしても、侵害となり得ると思われます。
問7
卸売市場において、育成者権侵害の可能性のある商品を取り扱うことに問題はあるのでしょうか。本来市場が有するのは集荷・分荷の役割です。卸売手数料をとるものの、原則的に生産者からの「委託」を受けて行われる卸売市場での売買は「仲介」といった意味合いが強く、商品の所有権は売手(委託者)から買手に移行するだけです。 そこで、育成者権の侵害品を卸売市場が取り扱った場合について質問します。
1.通常の競りなどで行われる取引のために、育成者権の侵害品を卸売市場のバックヤードに保管する行為は、種苗法第2条第5項の「これらの行為をする目的をもって保管する行為」に該当するのでしょうか。
答え
「譲渡」とは、有償無償を問わず、種苗等の所有権を移転する行為をいうと解されています(農林水産省生産局知的財産課編著「最新逐条解説種苗法」(以下、「最新逐条解説種苗法」という。)12頁)。 質問欄に記載のとおり、商品の所有権が売主である委託者から買主に直接移転するのであれば、上記の「譲渡」の定義からすると、卸売業者から買主に対して商品の「譲渡」があったといえず、売主から買主に対して商品の「譲渡」があったということになると思われます。
そうすると、本件では、保管者と譲渡者とが異なることになりますが、一般に、譲渡等をする者と保管者が異なることも想定されますので、他人がする譲渡等のために保管する行為に対し育成者権が及ばないと解するのは、育成者権保護の観点からは相当でないと考えられます。また、譲渡等をしようとする者が自ら保管する場合と、第三者が他者のする譲渡のために保管する場合とで、育成者権が受ける影響に変わりがあるとは考えられず、前者に効力が及ぶのに後者に効力が及ばないとする理由もないように思われます。
よって、卸売業者がバックヤードに保管する行為は、「これらの行為をする目的をもって保管する行為」に該当すると考えられます。
2.1が該当するとした場合、その行為者は卸売市場となり、卸売市場が育成者権の侵害を行ったことになるのでしょうか。それとも行為者は他者になるのでしょうか。
答え
保管行為を行っているのは卸売業者ですので、卸売業者が育成者権侵害を行ったことになると考えられます。また、委託した売主も、共同で侵害行為を行ったと評価される可能性があります。
問8
登録品種Xについて、小売店CでXの育成者権侵害と思われる切花が売られていました。Xの育成者権者Aは、その切花を出荷している農家Bがわかっており、BがXの種苗を無断増殖して切花を生産していることを知っていた場合について質問します。
1.Cが販売していたのはXの収穫物です。この収穫物にXの育成者権の効力は及びますか。
答え
育成者権の効力は、「品種」の利用に及びます(種苗法第21条第1項)。「品種」には、種苗だけではなく、収穫物も含まれますが(同法第2条第5項)、収穫物の利用に対して育成者権を行使できるのは、種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られます(同項第2号かっこ書き)。 このことは、育成者権の段階的行使の原則(カスケイド原則)といわれています。
2.BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花をCに出荷していることをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったことになりますか。
答え
種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」とは、種苗の段階において、育成者権者が登録品種を利用している第三者との間で許諾契約を締結することなどができる状況をいいます。 例えば、育成者権者において、当該第三者が登録品種を利用している事実を知っており、かつ、育成者権者が許諾により権利行使することが法的に可能であった場合には、「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったことになります。
したがって、育成者権者であるAが、Bによる登録品種Xの無断増殖の事実をいつの時点で知ったかによって、「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会」があったか否かが分かれます。
3.Bが昨シーズンからXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことをAが知っていた場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。
答え
Aは、Bにより登録品種Xの利用が昨シーズンから行われていたことを知っていたので、少なくとも今シーズンにおいては、Bとの間で許諾契約を締結する機会があったと考えられます。 このため、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」には該当しないと考えられます。
4.BがXの種苗を無断増殖し、生産した切花を出荷していたことを数日前にAが知った場合は、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当しますか。
答え
AはBによる登録品種Xの利用を数日前に知りましたが、その時点では既に収穫物の段階であり、種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する機会はなかったと考えられます。 このため、種苗法第2条第5項第2号かっこ書きの「(種苗の段階で)権利を行使する適当な機会がなかった場合」に該当すると考えられます。
5.AはCに対して切花の販売の差止を請求できますか。
答え
切花に対して育成者権の効力が及ぶ場合(その切花に係る種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合)には、Aは、Cに対し、種苗法第33条第1項の規定に基づき、切花の販売の差止を請求できます。
6.AはCに対して切花の販売に係る損害賠償を請求できますか。
答え
切花に対して育成者権の効力が及ぶ場合(その切花に係る種苗の段階においてBとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合)には、Aは、Cに対し、民法第709条の規定に基づき、切花の販売に係る損害賠償を請求できます。
なお、AがBに対し損害賠償を請求した場合には、その請求に係る切花の販売についてCに対して損害賠償を請求することはできないとされています。
仮保護について
問9
出願品種Yについて、小売店FでYと思われる切花が売られていました。その切花を出荷している農家がわからなかったため、 出願者DはFに対して警告を行いました。後に、当該切花を出荷していた農家Eが判明したのでEに対しても警告を行った場合について質問します。
1.Fが販売していたのはYの収穫物です。出願品種の収穫物の販売に対して警告できますか。
答え
種苗法第14条第1項の規定に基づく補償金支払請求は、出願品種の収穫物の利用者に対しても行うことができます。ただし、補償金支払請求権についてもカスケイド原則(問8の1参照)が適用されると考えられるため、種苗の段階で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に限られます。
2.Fは警告後もYの切花を販売していました。後に、当該切花を出荷していた農家がEであると判明しましたが、その後のFの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
答え
出願品種にもカスケイド原則が適用されると考えられるため、出願品種の収穫物に対する補償金支払請求は、種苗の段階で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に限られます。
DはEを知っていますが、出願品種の種苗の利用の事実を知ったのがいつの時点であったかによって、種苗の段階で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に該当するか否かが分かれます。
3.警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した当該シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
答え
DがEによる出願品種の種苗の利用を知ったのは収穫物の段階であり、種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する機会はなかったと考えられます。Eによる出願品種の種苗の利用が判明した当該シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になります。
4.警告後にFが販売した切花について、農家がEであると判明した翌シーズンの切花の販売行為は補償金支払請求の対象になりますか。
答え
Dは、Eによる出願品種の種苗の利用を知っていますので、翌シーズンの種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する機会があったと考えられます。そのため翌シーズンは補償金支払請求の対象にはならないと考えられます。
5.DがEとFに対して警告を発していた場合、警告後にFが販売した切花について、補償金の支払を請求できますか。
答え
Yの品種登録後に、Dは、Fに対し、種苗法第14条第1項の規定に基づき、切花の販売に係る補償金の支払を請求できます。ただし、その切花に係る種苗の段階においてEとの間で許諾契約を締結する適当な機会がなかった場合に限られます。
なお、DがEに補償金の支払を請求した場合は、その請求に係る切花の販売についてFに補償金の支払を請求することはできないとされています。
問10
種苗法における仮保護の期間と具体的な保護内容について教えて下さい。
答え
種苗法第14条に「出願公表の効果等」として「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第20条第2項各号に該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受けた場合にその利用に対しうけるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公表に係る出願品種(当該出願品種と特性により明確に区別されない品種及び当該出願品種が品種登録された場合に同項各号に該当することとなる品種を含む。以下この条において同じ。)であることを知って品種登録前にその出願品種を業として利用した者に対しては、同様とする。」とあります。
これがいわゆる「仮保護」に関する規定です。したがって、仮保護の期間は、出願公表された日から品種登録された日の前日までになります。また、具体的な保護内容は、警告後に業として出願品種等を利用した者に対して、その出願品種が登録された場合の利用料に相当する補償金請求をすることを認めることによって出願品種等の無断利用を防止することです。 なお、同条第2項に「前項の規定による請求権は、品種登録があった後でなければ、行使することができない。」とありますので、ご留意下さい。
問11
仮保護期間中の出願品種の利用について警告を行い、相手側が出願品種の種苗等を廃棄したと仮定します。その後、審査の結果、当該出願品種が登録されなかったために相手側から当該種苗の廃棄等で被った損害賠償を請求された場合、出願者はこの損害について賠償責任があるのでしょうか。
答え
種苗法第14条第1項は、「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、・・・補償金の支払いを請求することができる」と規定しており、登録前の出願者が、出願品種を業として利用する者に対し、補償金支払請求のため、警告することを許容しているといえます。
このように、登録前の出願者による警告は、法律により許容された行為であるといえることから、その警告が相当なものである限り、たとえ出願品種が審査の結果登録されなかったとしても、不法行為とはならないと考えられます。
よって、出願者の警告が法の趣旨目的に沿った相当なものである限り、出願品種が審査の結果登録されず、警告を受けた者がその警告により損害を被ったとしても、出願者は警告を受けた者に対し不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)は負わないものと思われます。
他方、出願者の警告が相当性を欠く場合、その警告は不法行為となり、出願者は出願品種の利用者に対し不法行為責任を負う可能性があります。例えば、出願品種が登録要件を欠くものであり、出願者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易に知り得たといえるのに、あえてその利用者に対して警告をしたような場合などは、当該警告は相当性を欠き不法行為となる可能性があると思われます。また、虚偽の事実を記載した書面による警告なども、相当性を欠くものと思われます。
「業として」の解釈について
問12
種苗法第20条第1項に、「育成者権者は、品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。
答え
種苗法第20条第1項の「業として」とは、個人的あるいは家庭的な利用を除く全ての行為を指します。ここでの解釈では、営利目的の有無は問いません。また、反復継続する必要もなく、ただ一回の利用であっても「業として」と判断されることがあります。
問13
「種苗法第4条第2項に、「品種登録は、・・・・・・・さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。」とありますが、「業として」とは具体的にどのような意味ですか。
答え
種苗法第4条第2項の「業として」の譲渡とは、反復若しくは継続の意思を持って譲渡することと解釈されており、20条の解釈とは少し異なります。営利目的の有無を問わないのは20条と同じです。 なお、継続の意思を持って行う譲渡には、一回の譲渡も含まれます。
品種登録について
問14
花きにおいて、花の部分に区別性がみられなくても、葉や茎などに区別性がみられれば、新品種として登録することは可能ですか。
答え
出願品種の審査は、それぞれの種類の特性表(農林水産省食料産業局知的財産課(以下、「知的財産課」という。)ホームページ「審査基準・特性表」の項目参照)の重要な形質について、日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確な違いがあれば「区別性」の要件を満たします。したがって、花の部分以外の特性において他と明確な違いがあれば登録されることとなります。ただし、登録されるためには区別性の他に、均一性、安定性、名称の適切性、未譲渡性の要件を満たす必要があります。
問15
出願にあたり、複数の人が同じ品種を出願しようとした場合、一番先に出願した人に権利が与えられるということですが、品種登録をしようとする場合、すでに同じものが出願されているかどうかを知ることはできるでしょうか。また、それはどのような手続きをとればよいのでしょうか。
答え
ご質問にありますように同時期に同一又は明確な区別性のない品種の育成が進んでいたような場合には、先願の品種が品種登録を受けることができます(先願主義)。 すでに同じものが出願されているかどうかを知るためには、「農林水産省品種登録ホームページ」の検索システムである「品種登録データ検索」(下記のURLを参照)等を利用してで出願公表された品種及び品種登録された品種を検索することができます。しかしながら、このホームページに掲載されている個々の品種特性情報は情報量に限りがあるため、さらに詳しくお知りになりたければ、出願公表中の品種であれば願書の閲覧・謄写が、登録品種であれば品種登録簿(特性値が記載されています)の閲覧・謄写が可能です。その手続きについては同課のホームページにてご確認いただくか、知的財産課の窓口(同課の種苗室(登録チーム:03-3502-8111(農林水産省大代表)))にお問合わせ下さい。
[参考]
農林水産省品種登録ホームページ
品種登録データ検索
問16
大豆の在来種について品種登録したいという要望があります。品種登録することが可能か教えて下さい。
答え
大豆の在来品種を品種登録したいとのことですが、在来品種は公知の品種であり、昔から流通しているものですので、品種登録の要件のうち未譲渡性に抵触し、品種登録はできません。
なお、当該在来品種を育種材料に用いて交配等を行い、在来品種と特性において明確に区別できる品種(系統)を育成すれば、それを品種登録出願することは可能です。また、品種登録の要件に「未譲渡性」がありますので、出願日より1年をさかのぼった日前に当該品種の種苗及び収穫物を日本国内で譲渡していないことが必要です。
問17
未譲渡性の要件の例外とされている「試験若しくは研究のための譲渡」に「新品種の育成のための譲渡」は含まれるでしょうか。
答え
ご質問の趣旨は、未譲渡性の要件の例外を定めた種苗法第4条第2項ただし書には「試験若しくは研究」とあるのに対して、育成者権の効力が及ばない範囲を定めた種苗法第21条第1項第1号には「新品種の育成その他の試験又は研究」と書かれているため、「新品種の育成」が「試験若しくは研究」に含まれるか否かをおたずねになったものと思います。
お答えとしては、以下の3点の理由から、種苗法第21条第1項第1号の「新品種の育成」は、「試験又は研究」に包含され、種苗法第4条第2項ただし書の「試験若しくは研究」についても、「新品種の育成」が含まれると解釈できます。
1.法律の条文の用字用語のルール上、「その他」という文言と、「その他の」という文言は使い分けられています。「その他」は、「その他」の前にある字句と後ろにある字句とが並列の関係にある場合に用いられます。他方、「その他の」は、「その他の」の前にある字句が、後にある字句の例示として、その一部を成している場合に用いられます。このルールからすると、種苗法第21条第1項第1号は、「その他の」と規定されていることから、前にある字句である「新品種の育成」は、後ろにある字句である「試験又は研究」の例示として、その一部を成している(「新品種の育成」は「試験又は研究」に包含される)ものということができます。
2.また、最新逐条解説種苗法101頁には、「試験研究目的の具体例としては、1新品種の育成のための交配に用いるために登録品種の種苗を増殖すること、・・・などが挙げられる」と記載されており、同書も「新品種の育成」は「試験又は研究」の例示と解しているものと考えられます。他方、「新品種の育成」を「試験又は研究」の例示と解することによる不都合はないと思われます。
3.種苗法第4条第2項ただし書は、ある出願品種が日本国内において1年(外国においては4年又は6年)より前に譲渡されたとしても、試験研究目的で譲渡された場合は、流通を目的としたものではなく流通範囲が限定されていること、円滑な品種の育成等を図る要請があることから、例外的に許容されることとしたものです(「最新逐条解説種苗法」35頁)。このような同条の趣旨は、新品種育成のための試験研究の場合でも該当すると思われます。これに加え、同条ただし書きの「試験若しくは研究」に新品種の育成の場合を除く旨の規定もなく、新品種の育成の場合を除かなければ不都合を生じるとも思われないことからすると、新品種の育成のための試験研究を、同条項の「試験若しくは研究」から除外して考える理由はないように思われます。
登録品種の育種への利用について
問18
新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思いますが、親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。
答え
種苗法では登録品種を育種素材として利用する場合には育成者権者の許諾が不要であると規定しており(種苗法第21条第1項第1号)、利用が許されない場合はないとされています。
ただし、変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成した場合(従属品種)やその品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる場合(交雑品種)には、当該登録品種の育成者権の効力がそれらの品種にまで及ぶとされています(種苗法第20条第2項)。
農業者の自家増殖
問19
観植物の鉢物について、農家が登録品種100鉢の苗を買い、それを1000鉢に増殖して販売することはできますか。
答え
農業者の自家増殖は、種苗法第21条第2項で、「農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種(以下[登録品種等]と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、そのさらに用いた種苗及びこれを用いて得た収穫物には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。」と規定されています。したがって、購入した苗から挿し穂(挿し穂を収穫物とみなす)を採り、挿し木により増殖した植物を収穫物として販売することは可能です。また、増殖できる数量にも特に制限はありませんし、増殖を繰り返し行うこともできます。ただし、注意点が3つあります。
1つ目は、最初に入手する種苗については、育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された正規のものでなければなりません。ホームセンター等で売られているものは種苗ではなく収穫物として販売されていることが多いので注意が必要です。
2つ目は、自家増殖が認められない種類があることです。種苗法施行規則第16条で自家増殖が認められない種類が指定されています(現在82種類)。バラやカーネーションは自家増殖が認められません。
3つ目は、種苗の入手に際する契約において自家増殖禁止の合意をしているかどうかです。契約中に自家増殖禁止の条項があれば、自家増殖は契約違反になりますし、育成者権侵害にもなります。
問20
種子繁殖性の観賞植物について、農家が登録品種の種子を買い、それを基に自家採種によって得た種子から育てた植物を販売することはできますか。
答え
種子繁殖性の観賞植物の品種を自家採種によって増殖する行為も農業者の自家増殖の範囲内であると解釈されています。この場合の注意点も問19と同じです。
問21
農家が登録品種の苗を買い、それを業者に委託して増殖することを考えています。生産された種苗はすべて引き取り、外部へ流出することはありません。この場合、農業者の自家増殖の範疇といえるのでしょうか。
答え
業者に委託して種苗を増殖する行為は農業者の自家増殖とは認められません。農業者の自家増殖は、種苗を用いて得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用することであり、外部の業者に種苗の増殖を委託することはできません。
問22
種苗法において自家増殖が制限されている栄養繁殖植物に属さない登録品種の種苗を以下のように用いた場合には育成者権の侵害になりますか。
1.農家が隣の家から種を分けてもらい栽培し,直売所で販売している場合
答え
隣の家から分けてもらった種子が、隣の家が正規に入手(育成者権者等の権利者若しくは権利者の許諾を得た種苗会社又は卸・小売業者等適正な流通経路から入手)したそのものの種子である場合は、権利が消尽した種子であるので、権利侵害にはなりません。
しかしながら、その種子が隣の家で増殖した種子であった場合は、その種子は権利が消尽しておらず、その種子を利用する行為は権利侵害となります。なお、隣の家の行為(種苗を増殖して第三者に譲渡)ついても権利侵害となります。
2.農家が食用として販売されている豆を自分の畑にまき,収穫物を得て販売している場合
答え
食用として販売されている豆を種子に転用し、収穫物を得て販売することは、法律上認められた自家増殖ではなく、許諾を受けずに種苗を利用したこととなり、権利侵害に当たります。
3.生産組合や集落営農組織が種子を購入し,それを増殖して組合員に配布する場合
答え
生産組合等が農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人)である場合は、自家増殖となり権利侵害にはなりませんが、農業生産法人でない場合、正規に種子を入手したとしても、当該種子を増殖・配布する行為については権利侵害となります。
問23
海外では自家増殖に対してもロイヤリティが発生すると聞きましたが、日本においては、自家増殖については利用権が発生しないと考えてよいのでしょうか。
答え
いわゆる自家増殖については各国の法律での取扱いに違いがあります。我が国の種苗法では、農業者個人又は農業生産法人が最初に育成者権者より譲渡された種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は及ばないこととなっています。ただし、省令で定めた種類(現在82種類)の栄養繁殖植物や契約で別段の定めをした場合には、こうした自家増殖にも育成者権の効力が及びますので注意して下さい。
問24
農業者の自家増殖によって造成した登録品種の果樹園の貸渡し、譲渡及び相続について教えてください。
1.当該果樹園を貸し渡すことはできますか。
答え
果樹の成木は収穫物に該当すると考えられますので(最新逐条解説種苗法107頁)、農業者の自家増殖によって作られた果樹の成木を貸し渡す行為については、種苗法第21条第2項「・・・育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。・・・」によって、改めて育成者権者の許諾を得る必要はなく、当該果樹園は適法に貸し渡すことができます。
2.当該果樹園を借り受けた者が収穫した果実を販売することはできますか。
答え
農業者の自家増殖は、種苗から収穫物を得ることを反復継続して行っている農業者が、従前からの慣行として、収穫物の一部を自己の農業経営における次期作用の種苗として使用し、次期作においてこれを栽培して収穫物を得ていたことから、例外的に育成者権の効力を及ぼさないとしているものです。このことは、収穫物を種苗として用いる行為のみならず、その種苗を用いて収穫物を得る行為についても、自己の農業経営において行われることが想定されていると考えられます。
したがって、条文上は必ずしも明確ではありませんが、自己の農業経営ではないところで得られた収穫物については、育成者権が及ぶと解される可能性がありますので、当該果樹園の借受人が育成者権者に無断で果実を生産し、販売等を行うことは、育成者権の侵害になる可能性があると思われます。
もっとも、当該果樹園の借受人の農業経営が貸渡人の農業経営と同視できるような場合(農業により得られる経済的利益が基本的に貸渡人に帰属し、借受人は貸渡人の補助的な位置づけにすぎないような場合など)は、自己の農業経営において収穫物を得たと考えることができると思われます。
3.当該果樹園を譲渡することはできますか。
答え
1と同じ理由で当該果樹園は適法に譲渡することができます。
4.農業者の自家増殖によって造成された登録品種の果樹園を譲り受けた者が収穫した果実を販売することはできますか。
答え
2と同じ理由で、当該果樹園を譲り受けた者が育成者権者に無断で果実を生産し、販売等を行うことは育成者権の侵害になる可能性があると思われます。
ただし、農業経営を包括的に譲渡した場合(農場全体を売却したような場合)、これを譲り受けた者の農業経営が、譲渡人の「自己の農業経営」に該当し、継続して適法に果実を生産し販売することが可能と解釈される余地があります。
なお、いずれにせよ育成者権者の許諾を受けることが安全と思われます。
5.当該果樹園を相続した者が収穫した果実を販売することはできますか。
答え
当該果樹園を相続した者が、そこから得られた収穫物を販売する行為は、民法第896条により、相続人は育成者権に関する一切の権利を承継しているので、改めて育成者権者の許諾を得なくとも適法に行えると考えられます。
しかし、相続人が「農業を営む者」でなかった場合は、改めて育成者権者の許諾を得る必要があります。
「農業を営む者」は、種苗法施行令第5条で、「農業を営む個人」又は農地法第2条第3項に規定する「農業生産法人」とされています。このうち「農業を営む個人」の定義は明確ではありませんが、反復継続の意思を持って農業を行う者であれば、「農業を営む個人」に該当すると解されますので、誰でもその意思をもって農業を行うのであれば「農業を営む個人」になり、実質的には問題はないと考えられます。
→常緑キリンソウに関する重要なお知らせ:種苗法TOPに戻る
→種苗法・品種育成者権とは→種苗法違反事件の事例・育成者権侵害の事例につて
→種苗法条例TOPへ→種苗法用語集TOPへ
→常緑キリンソウ(常緑キリン草・常緑麒麟草)の特徴TOPへ
→常緑キリンソウ袋方式・FTMバック・緑の夢袋プロジェクTOPへ
→常緑キリンソウ施工事例TOPへ
→屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com TOPに戻る